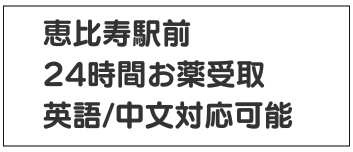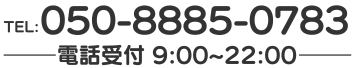最終更新:2025-10-19/監修:金谷 正樹 医師(日本性感染症学会 会員)
【30秒で理解】梅毒の要点
- 原因と感染経路:梅毒は「梅毒トレポネーマ」という菌が原因の性感染症です。主な感染経路は、性行為による皮膚や粘膜の直接的な接触です。
- 症状の変化:症状は時間経過で変化します(第1期→第2期→晩期)。初期は痛みのないしこり、その後手のひらや足の裏を含む全身の発疹などが出現しますが、自然に消えるため発見が遅れがちです。
- 母子感染のリスク:妊娠中の方が感染すると、胎盤を通じてお腹の赤ちゃんにも感染する「先天梅毒」のリスクがあります。
- 検査と治療:血液検査で診断します。治療の第一選択はペニシリン系の抗菌薬で、当院では1回の筋肉注射による治療も可能です。
- 法的側面:梅毒は感染症法で「五類感染症」に定められており、診断した医師には全数届出が義務付けられています。
【目次】
1. 梅毒の基本情報(原因菌・感染経路)
- 原因菌:梅毒トレポネーマ(Treponema pallidum)という、らせん状の細菌です。ヒトのみを宿主とします。
- 主な感染経路:性行為(オーラルセックス、アナルセックスを含む)の際に、感染部位の皮膚や粘膜が直接接触することで感染します。菌は非常に小さいため、目に見えないような傷からも侵入します。
- 菌の性質:酸素や乾燥に非常に弱く、人の体外では短時間で死滅します。そのため、衣類や食器、入浴施設などを介して感染する可能性は極めて低いと考えられています。
2. 梅毒の症状(時期ごとの変化と見分け方)
梅毒の症状は、感染後の期間によって大きく3つの段階に分けられます。特徴は、症状が出ても治療をしないまま自然に消えてしまう点です。しかし、症状が消えても治ったわけではなく、体内で静かに進行していきます。
| 病期 | 時期の目安 | 主な症状・特徴 |
|---|---|---|
| 早期梅毒(第1期) | 感染後 約3週間~3か月 | 菌が侵入した部位(性器、口、肛門など)に痛みのない硬いしこり(硬性下疳)や潰瘍ができる。足の付け根のリンパ節が腫れることも。症状は自然に消える。 |
| 早期梅毒(第2期) | 感染後 約3か月~3年 | 菌が血流にのって全身へ。「バラ疹」と呼ばれる体幹の発疹、特に手のひら・足の裏にできる発疹が特徴的。発熱、倦怠感、咽頭痛など多彩な症状。症状は再発を繰り返しながら消える。 |
| 晩期梅毒 | 感染後 数年~数十年 | 皮膚のゴム腫、心臓・血管や脳、神経に深刻な障害をきたす。現在の日本では稀。 |
※神経梅毒について:頭痛、めまい、難聴、視力低下などの神経症状は、上記のどの病期でも起こり得ます。
3. 梅毒の検査(検査方法・タイミング・注意点)
検査で何を調べるのか?
血液検査で、梅毒トレポネーマに対する2種類の抗体(体の防御反応で作られるタンパク質)を測定します。
- 非トレポネーマ抗体検査(RPR法など):現在の病気の活動性(勢い)を反映します。数値で測定(定量)し、治療効果の判定にも用います。
- トレポネーマ抗体検査(TP法など):過去に感染したことがあるか否かを調べます。一度陽性になると、治療後も生涯陽性のまま残ることが多いです。
→当院では、この2種類を組み合わせて正確な診断を行います。
検査のタイミング(ウィンドウ・ピリオド)
感染してすぐに検査をしても、抗体がまだ作られていないため陰性(偽陰性)となる「ウィンドウ・ピリオド」があります。感染機会から4週間以降の検査が望ましいとされています。
偽陽性の可能性について
妊娠、自己免疫疾患、一部の感染症など、梅毒とは無関係の原因でRPR法が陽性(偽陽性)となることがあります。そのため、必ずTP法と組み合わせて最終的な診断を行います。
4. 梅毒の治療(第一選択薬・治療後の経過)
梅毒は、早期に発見し、適切な抗菌薬(抗生物質)で治療すれば完治が可能です。
- 第一選択薬:ペニシリン系の抗菌薬が最も効果的です。病期に応じて、内服(飲み薬)または筋肉注射で治療します。当院では、早期梅毒に対して1回の来院で治療が完了する筋肉注射製剤(ステルイズ®)を第一選択としています。
- Jarisch–Herxheimer反応:治療開始後、数時間以内に一時的な発熱、悪寒、頭痛、発疹の悪化などが現れることがあります。これは菌が破壊される際の反応で、治療が効いている証拠でもあります。通常は1~2日で自然に軽快します。
- 治療後の再検査:治療が終わっても、完治したことを確認するために定期的な血液検査(RPR法の定量値の追跡)が不可欠です。数値が十分に低下するまで、医師の指示に従って通院が必要です。
5. 妊娠と梅毒(先天梅毒のリスク)
妊娠中の方が梅毒に感染すると、胎盤を通じて胎児にも感染し、流産、早産、死産や、赤ちゃんに障害が残る「先天梅毒」の原因となります。妊婦健診でのスクリーニングと、リスクがある場合の早期治療が極めて重要です。
6. 予防とパートナーへの対応
- 予防の基本:コンドームを正しく使用することで、コンドームが覆う部分の感染リスクは大幅に減少します。しかし、覆われていない皮膚や粘膜からの感染は防げないため、100%ではありません。
- 【新しい予防法】Doxy-PEP(ドキシペップ):性行為の後72時間以内に抗菌薬であるドキシサイクリンを内服することで、梅毒やクラミジアなどの性感染症のリスクを低減させる予防法です(曝露後予防内服)。まだ新しい方法であり、医師の診察と処方が必要ですので、ご希望の方はご相談ください。
- パートナーへの対応:ご自身が陽性と診断された場合、症状がなくてもパートナーが感染している可能性があります。再感染(ピンポン感染)を防ぐためにも、パートナーの検査・治療が不可欠です。
7. 法的取り扱いと国内の動向
- 感染症法上の位置づけ:五類感染症に分類され、診断した医師は直ちに保健所に届け出る義務があります(全数把握対象疾患)。
- 国内の動向:日本の梅毒報告数は近年急増しており、特に若年層での感染拡大が問題視されています。
8. よくある質問(FAQ)
Q1. オーラルセックスだけでも感染しますか?
A. はい、感染します。性器と口の接触でも、口内や咽頭の粘膜から菌が侵入し、感染の原因となります。
Q2. 一度治れば、もう二度とかかりませんか?
A. いいえ、何度でも再感染します。治療で完治しても、感染を防ぐ免疫ができるわけではありません。新たな感染機会があれば、再び感染します。
Q3. 検査はいつ受ければいいですか?
A. 感染の心当たりがある日から、4週間以上経過してからの検査を推奨します。それ以前の検査で陰性でも、感染を否定できない場合があります。
Q4. パートナーに何と伝えればよいですか?
A. 「自分に梅毒が見つかったので、症状がなくてもうつしている可能性があるから、検査を受けてほしい」と正直に伝えることが大切です。当院では、パートナーへの説明方法についてもご相談いただけます。
9. 参考文献・出典
- 日本性感染症学会. 性感染症 診断・治療 ガイドライン 2020
- 国立感染症研究所. 梅毒とは
- 厚生労働省. 性感染症