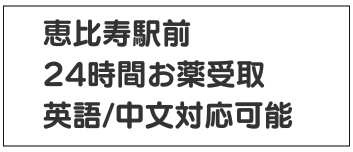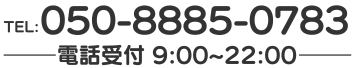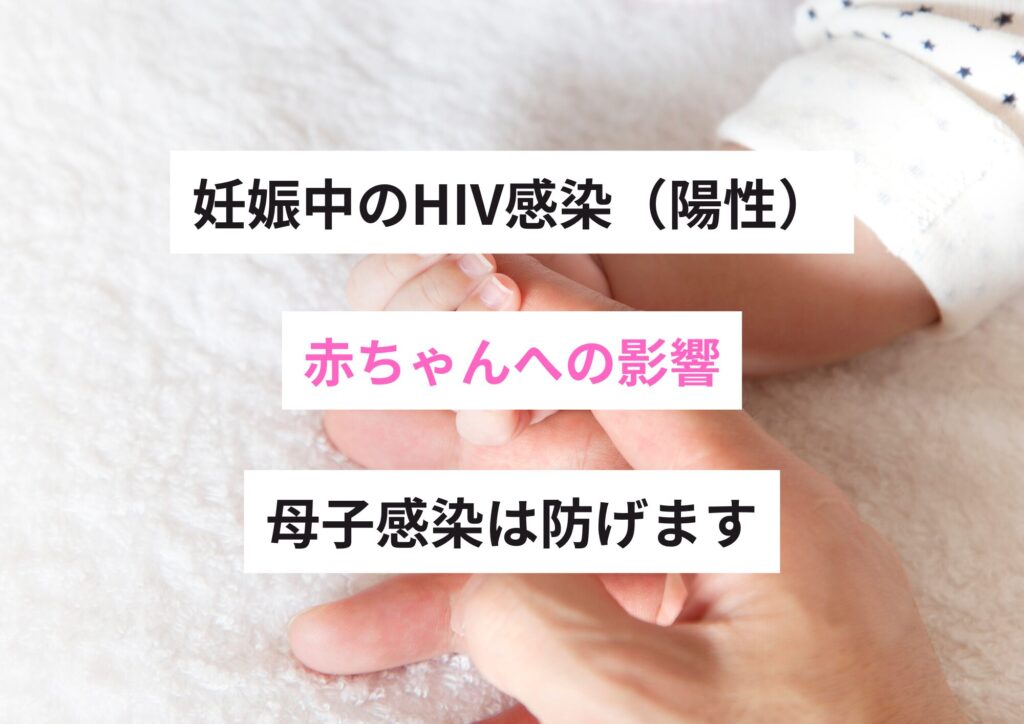
妊娠がわかった方、妊娠を考えている方へ
「お腹の赤ちゃんに感染したらどうしよう…」
今、言葉にできないほどの不安でいっぱいだと思います。
まず、一番大切なことをお伝えします。
適切な治療と管理を行えば、
赤ちゃんへの母子感染のリスクは
1%未満(限りなくゼロ)に抑えられます。
あなたは一人ではありません。正しい知識を持って、赤ちゃんの未来を守るために、私たちが全力でサポートします。
このページの要点
- 妊娠がわかったら、できるだけ早く専門医に相談し、抗HIV薬治療(ART)を開始・継続することが最も重要です。
- 「妊娠中の治療」「分娩方法の選択」「赤ちゃんへの予防内服」「授乳を避ける」の4つを柱に対策します。
- 日本では、感染リスクをゼロにするため、母乳は避けて人工乳(粉ミルク)で育てることが原則です。
妊娠とHIVについてのご相談・検査はこちら
当院は、専門医療機関への「橋渡し役」として、あなたの不安な初期段階を支えます。→ HIV検査の予約・相談(恵比寿)
目次
- 1. Q. 日本の「母子感染予防」の基本方針は?
- 2. Q. 妊娠がわかったら、まず何をすべき?
- 3. Q. 出産方法は? 帝王切開は必須ですか?(クリックして確認)
- 4. Q. 生まれた後の赤ちゃんへのケアは?(予防内服)
- 5. Q. 赤ちゃんのHIV検査はいつしますか?
- 6. Q. 母乳(授乳)はあげられますか?
- 7. Q. パートナーや家族のサポートは?
- 8. 当院でできること(恵比寿・モイストクリニック)
- 9. よくあるご質問(FAQ)
1. Q. 日本の「母子感染予防」の基本方針は?
結論:妊娠中からの「抗HIV薬治療(ART)」を柱に、「分娩管理」「赤ちゃんへの予防内服」「母乳を避ける」を組み合わせて、母子感染のリスクを限りなくゼロに近づけます。
日本では、以下の対策を組み合わせることで、母子感染率を劇的に下げることに成功しています。
- 母親:妊娠中から抗HIV薬治療(ART)を開始・継続し、ウイルス量を検出限界未満に抑えます。
- 出産時:ウイルス量に応じて、経腟分娩または帝王切開を選択します。
- 赤ちゃん:出生直後から、予防的に抗HIV薬(シロップなど)を一定期間内服します。
- 授乳:母乳による感染リスクをゼロにするため、人工乳(粉ミルク)で育てます(母乳遮断)。
(出典:HIV母子感染予防対策マニュアル(第9版))
2. Q. 妊娠がわかったら、まず何をすべき?
結論:できるだけ早く、エイズ診療拠点病院などの専門医療機関を受診してください。
妊娠が判明した(またはHIV陽性で妊娠を希望する)場合、最も重要なのは、産科・小児科・内科が連携して治療にあたれる専門機関へ速やかに繋がることです。
- 初期相談・連携:まずは当院のようなクリニックにご相談ください。すぐに専門医療機関へご紹介します。
- 評価と治療(ART)開始:専門機関で、現在の免疫力(CD4)やウイルス量(HIV RNA)を調べ、抗HIV薬治療(ART)を開始または継続します。
- ウイルス量の管理:妊娠後期までにウイルス量を「検出限界未満」に維持することが、母子感染予防の最大の鍵となります。
3. Q. 出産方法は? 帝王切開は必須ですか?
結論:いいえ、必須ではありません。分娩直前のウイルス量によって、経腟分娩も選択可能です。
かつては帝王切開が推奨されていましたが、現在は治療が進歩したため、以下のように判断されます。
【A】ウイルス量が「検出限界未満」で安定している場合
→ 経腟分娩 が選択可能です。
日本のガイドライン(第9版)でも、ウイルス量が安定して抑えられていれば、経腟分娩を許容できるとされています。ただし、施設の体制なども含めて専門医が総合的に判断します。
【B】ウイルス量が多い(VL≧1,000 copies/mL)または不明な場合
→ 計画的帝王切開(38週目安)が推奨されます。
赤ちゃんが産道を通る際の感染リスクを避けるため、陣痛が始まる前に帝王切開で出産することが推奨されます。(出典:NIH/HHS, ACOG)
4. Q. 生まれた後の赤ちゃんへのケアは?(予防内服)
結論:出生直後から、赤ちゃんにも予防的に抗HIV薬(シロップ)を飲んでもらいます。
お母さんのウイルス量(=赤ちゃんへの感染リスク)に応じて、予防内服の強さが変わります。
- 低リスクの場合(母親のウイルス量が検出限界未満):AZT(ジドブジン)というお薬1種類を、一定期間(例:2~4週間)内服します。
- 高リスクの場合(母親のウイルス量が高い、未治療など):3種類のお薬を組み合わせるなど、より強力な予防内服を一定期間(例:4~6週間)行います。
どのお薬をどのくらいの期間続けるかは、小児科の専門医が判断します。(出典:HIV母子感染予防対策マニュアル(第9版))
5. Q. 赤ちゃんのHIV検査はいつしますか?
結論:生後数ヶ月かけて、複数回検査(NAT)を行い、感染の有無を最終的に確認します。
生まれたばかりの赤ちゃんは、お母さんからのHIV抗体を(感染していなくても)持っているため、抗体検査は使えません。そのため、ウイルス遺伝子そのものを調べる「核酸検査(NAT)」で行います。
一般的な検査スケジュール(NIH推奨)
- 1回目:生後14~21日
- 2回目:生後1~2ヶ月
- 3回目:生後4~6ヶ月
※高リスクの場合は、出生直後にも検査を追加することがあります。
最終的なスケジュールは、小児科専門医の指示に従ってください。
6. Q. 母乳(授乳)はあげられますか?
結論:日本では、赤ちゃんへの感染リスクをゼロにするため、原則として母乳は避け、人工乳(粉ミルク)で育てます。
HIVは母乳を介しても感染する可能性があります。治療(ART)でウイルス量を抑えていても、そのリスクを完全にゼロにすることは難しいとされています。
- 日本の基本方針:母子感染予防対策の一環として「母乳遮断」(母乳を与えず、粉ミルクやドナーミルクで育てる)が確立されています。
- 国際的な情報:CDC(アメリカ疾病予防管理センター)も、粉ミルクなどの代替栄養が、出生後の感染リスクをほぼゼロにできるとしています。
※WHO(世界保健機関)は、衛生的な水や粉ミルクが手に入りにくい資源制約地域では、ART継続下での母乳育児を推奨していますが、これは日本の状況とは異なります。日本の医療機関では、主治医の方針に従ってください。
7. Q. パートナーや家族のサポートは?
結論:パートナーの検査や、公的な医療費助成制度の利用が重要です。
- パートナーの検査:お母さんが陽性の場合、パートナーもHIV検査を受けることが非常に重要です。保健所などを通じて匿名で検査を勧めることも可能です。
- 医療費助成:HIV治療は公的保険が適用され、さらに「自立支援医療(更生医療)」や「高額療養費制度」の対象です。妊娠・出産に関わる費用についても、専門病院のソーシャルワーカーが相談に乗ってくれます。
8. 当院でできること(恵比寿・モイストクリニック)
私たちは、専門医療機関へお繋ぎするまでの「最初の相談窓口」です。
妊娠中に陽性が判明した時、あるいは陽性で妊娠を考えた時、その不安は計り知れません。専門病院の予約を取るまでの間、誰にも相談できず一人で抱え込んでしまう方も少なくありません。
モイストクリニックは、そんなあなたの「最も不安な初期段階」に寄り添う「橋渡し役」でありたいと考えています。
- 妊娠判明時の初期相談、HIV検査(即日)を、プライバシーに配慮した環境で行います。
- 結果が陽性だった場合、パニックにならず次の行動に移せるよう、専門医が丁寧にご説明します。
- 母子感染予防の実績が豊富な「エイズ診療拠点病院」へ、当院が責任を持って速やかにご紹介・連携します。
一人で悩む前に、まずは私たちにご相談ください。
9. よくあるご質問(FAQ)
Q1. 妊娠中に抗HIV薬を飲んでも、赤ちゃんに影響はありませんか?
A. 妊娠中に安全に使用できると確認されているお薬が多数あります。治療を継続し、ウイルス量を抑えることのメリット(母子感染を防ぐこと)は、お薬のリスクをはるかに上回ります。専門医があなたに合った安全な薬を選択します。
Q2. 妊娠がわかってから治療を始めても間に合いますか?
A. はい、間に合います。妊娠がわかったら、できるだけ早く治療(ART)を開始することが重要です。早く始めれば、分娩までにウイルス量を検出限界未満にできる可能性が非常に高くなります。
Q3. 治療費や出産費用が心配です。
A. HIV治療は公的医療保険に加え、「自立支援医療(更生医療)」の対象です。所得に応じた自己負担上限額が設定され、負担は大幅に軽減されます。出産費用についても、専門病院のソーシャルワーカーが利用できる制度を一緒に探してくれます。
モイストクリニック(恵比寿)のご案内
モイストクリニックは、東京都渋谷区恵比寿にある【性感染症・男性科・婦人科】の専門クリニックです。
プライバシーに配慮した診療体制で、初めての方でも安心してご相談いただけます。
当院では、対面・オンラインのどちらでも診療が可能。お仕事やご予定の合間でも受診しやすいよう、平日夜間(22時まで)や土日祝日も診療しています。
LINE公式アカウントでは、
🟢 ちょっとしたご相談も気軽にメッセージで受付中
🟢 検査・診療のご予約もLINEから24時間OK
🟢 受診に関するご質問も匿名でOK
と、身近なパートナーとしていつでもご利用いただけます。
まずはお気軽にLINEで友だち追加してみてください👇
▶ LINEで友だち登録する
【アクセス】
〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-2-1 エビスマンション610
(JR「恵比寿駅」西口より徒歩3分)
➡️ クリニックへの詳しい道順はこちら
【ご予約・お問い合わせ】
📱 LINE: @696ufkcc(友だち追加で予約・相談OK)
📞 電話:050-8885-0783(「ホームページを見た」とお伝えいただけるとスムーズです)
💻 Web予約:LINEから24時間受付中!
症状に心当たりのある方や不安がある方も、ぜひ一度ご相談ください。
モイストクリニックは、あなたの健康と安心のために、丁寧にサポートいたします。
🔖 監修者情報

監修:モイストクリニック院長 金谷 正樹
国際医療福祉大学病院、東京医科歯科大学病院(現東京科学大学病院)などで研鑽を積み、モイストクリニックで性感染症を中心に診療を行っている。日本性感染症学会の会員として活動しており、得意分野である細菌学と免疫学の知識を活かして、患者さまご本人とパートナーさまが幸せになれるような医療を目指している。
🖊️ この記事の執筆者

監修:泌尿器科医 宮田(モイストクリニック)
国立信州大学医学部医学科を卒業後、川崎市立井田病院にて初期研修を修了。都内大学病院の泌尿器科に入局し、性感染症分野で専門性を深める。
日本性感染症学会、日本感染症学会、日本性機能学会などに所属し、現在は薬剤耐性淋菌に対する新規抗生剤の研究に携わりながら、性感染症および泌尿器科疾患の診療にあたっている。
【この記事を読んだあなたへ】
妊娠という喜ばしい出来事と、HIVという診断が重なり、あなたの心は今、張り裂けそうかもしれません。しかし、日本の母子感染予防医療は世界最高水準です。正しいステップを踏めば、必ず道は拓けます。私たちはその最初の一歩を支えるためにいます。
参考文献・公的情報
- 厚生労働省「HIVとエイズ」:感染経路・母子感染の基礎
- HIV母子感染予防対策マニュアル(第9版):日本の臨床ガイドライン
- NIH/HHS (アメリカ国立衛生研究所)|Recommendations for the Use of Antiretroviral Drugs During Pregnancy
- CDC (アメリカ疾病予防管理センター)|HIV and Perinatal Transmission
- ACOG (アメリカ産科婦人科学会)|HIV and Pregnancy
- WHO (世界保健機関)|HIV/AIDS