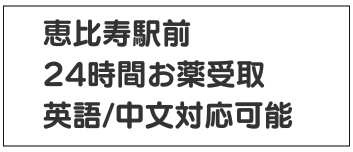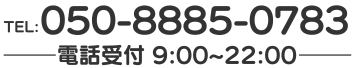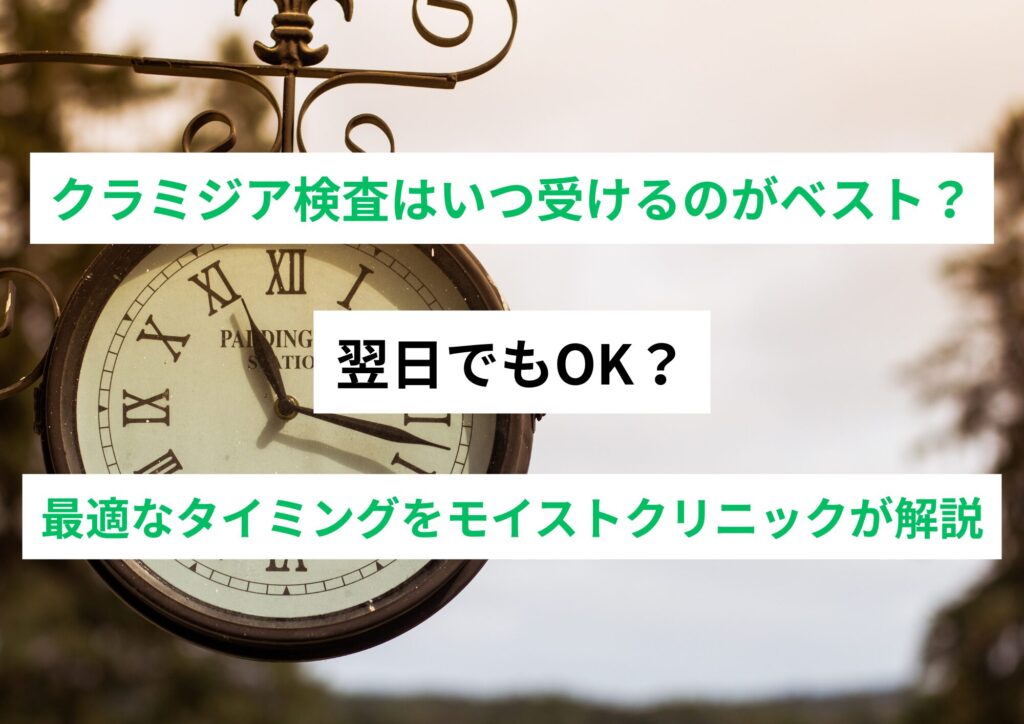
「もしかしてクラミジアに感染したかも…?」
「性行為の翌日だけど、もう検査はできる?」
パートナーの感染がわかったり、少しでも不安な行為があったりすると、一刻も早く検査を受けたいと思うのは当然のことです。
この記事では、性感染症専門のモイストクリニックが、国内外の公的なガイドラインに基づき、「クラミジア検査を受けるべき最適なタイミング」を分かりやすく解説します。
先に結論をお伝えします。
- 不安を感じたら、まずは“すぐ検査”で大丈夫です(感染機会の翌日でも検査自体は可能)。
- ただし、より確実を期すために、最終接触が2週間以内なら「2週間後にもう一度検査」するのが最も安心です。
- 治療後は、再感染の確認のため「約3か月後」の再検査が推奨されています。
この記事を読めば、あなたの状況に合った「受けどき」が分かり、不要な心配を解消できます。
なぜ「すぐ検査」と「2週間後の再検査」が推奨されるの?
感染症の検査には、ウイルスや細菌が体内で十分に増殖し、検査で検出できるようになるまでの「ウィンドウピリオー(またはウィンドウ期間)」が存在します。
クラミジアの場合、感染後すぐに検査をしても、菌の量が少なすぎて「陰性(感染していない)」と誤って判定されてしまう可能性があるのです。
- すぐ検査するメリット:現在の感染状況を暫定的に確認でき、万が一陽性なら早期治療に入れる。何より「まず行動した」という安心感が得られる。
- 2週間後に再検査する意味:菌が増えて検出感度が安定する時期のため、初期の「見逃し(偽陰性)」を防ぎ、最終的な確定診断ができる。
この考え方は、英国の国民保健サービス(NHS)の患者向け資料でも示されており、「すぐに検査は可能だが、見逃しを避けるため2週間後の再検査を勧めることがある」とされています。
だからこそ、「不安な今すぐの検査」と「念のための2週間後の再検査」という2段階の構えが、最も合理的で安心できる方法なのです。
【早見表】あなたの状況はどれ?状況別の最適な検査タイミング
ご自身の状況に合わせて、いつ検査を受けるべきか、以下の表でご確認ください。
| 状況 | まず、いつ検査? | 追加検査の目安は? | 理由・ポイント |
|---|---|---|---|
| リスクのある行為の翌日〜14日未満 | すぐに検査を(推奨) | 最終接触の2週間後に再検査 | 早期の偽陰性リスクを考慮。「すぐ検査+2週間後再検査」で確実性を高めます。 |
| リスクのある行為から14日以上経過 | すぐに検査を受けるべき | 症状や行為部位に応じ医師が判断 | 2週間以上経てば検出感度は安定。一度の検査でほぼ確定できます。 |
| 排尿痛・おりもの・のどの違和感など症状がある | 今すぐ検査を | 必要に応じて再検査 | 症状は体からのサイン。合併症を防ぐため、一日も早い診断と治療が重要です。 |
| パートナーが陽性と判明 | 今すぐ検査を | 直近の接触が2週以内なら2週間後に再検査 | パートナーが陽性の場合、ご自身も感染している可能性が高いです。早期介入で見逃しを防ぎます。 |
| 治療を終えた後 | ー | 約3か月後に再検査(再感染チェック) | 治癒したかの確認ではなく、新たな感染(再感染)がないかを確認します。 |
| 妊娠中に陽性になった | ー | 治療4週後に治癒確認+3か月以内に再検査 | 妊娠中は胎児への影響を考慮し、しっかり治癒したかを確認(TOC)します。 |
どの検査が一番いい?精度が高い検査方法と正しい検体の採り方
クラミジア検査で現在、最も精度が高いとされているのは「NAAT(核酸増幅検査)」です。PCR法やTMA法などがこれに含まれます。
モイストクリニックでは、この高感度なNAATを採用しています。
そして、正確な結果を得るためには、「正しい部位から」「正しく」検体を採取することが非常に重要です。
- 検査方法:第一選択はNAAT(PCR/TMA法など)です。
- 検体(女性):自己採取による膣(ちつ)スワブ(VVS)が第一選択です。医師による内診台での採取は不要で、ご自身で簡単に採取できます。
- 検体(男性):初尿(first-catch urine)が推奨されます。出始めの尿が最も菌を検出しやすいためです。
- 検査する部位:性的な接触があった部位(尿道・膣・のど・肛門)すべての検査を検討することが大切です。オーラルセックスのみでも、のどのクラミジア(咽頭クラミジア)に感染します。
【検査前のワンポイントアドバイス】
男性が尿検査を受ける際は、最後の排尿から最低1〜2時間は空けてから採尿すると、尿道内の菌が洗い流されず、検査の精度が上がります。ご来院前に少しだけ排尿を我慢していただくと、より正確な結果に繋がります。
治療後の「陰性確認」を急いではいけない理由
「治療が終わったから、すぐに陰性になったか確認したい」というお気持ちはよく分かります。
しかし、クラミジア治療後、3〜5週間は体内に死滅した菌のDNAが残っていることがあります。この時期にNAAT(PCR検査など)を受けると、生きている菌はいないのに「陽性」と出てしまう「偽陽性」のリスクがあるのです。
そのため、ガイドラインでは、妊娠中などの特別なケースを除き、治療後の治癒確認検査(Test of Cure: TOC)は原則不要とされています。
治ったかどうかではなく、「新たな感染(ピンポン感染など)をしていないか」をチェックするために、米国疾病予防管理センター(CDC)は約3か月後の再検査を推奨しています。
放置は危険!検査をためらっているあなたへ
クラミジアは「沈黙の感染症」とも呼ばれ、特に女性の約8割、男性の約5割は自覚症状がありません。
しかし、症状がないからと放置すると、気づかないうちに進行し、深刻な合併症を引き起こす可能性があります。
- 女性の場合:骨盤内炎症性疾患(PID)を引き起こし、不妊症や子宮外妊娠の重大な原因になります。
- 妊娠中の場合:産道で赤ちゃんに感染し、新生児結膜炎や肺炎を引き起こすリスクがあります。
- 男女共通:尿道炎、精巣上体炎(男性)、咽頭炎などを引き起こします。
少しでも心当たりがあるなら、将来の自分のため、そして大切なパートナーのために、勇気を出して検査を受けることが重要です。
【恵比寿・渋谷エリアの方へ】モイストクリニックでできること
恵比寿駅すぐのモイストクリニックは、お仕事帰りや買い物のついでにも立ち寄りやすい、プライバシーに配慮した性感染症専門クリニックです。渋谷区、目黒区、港区(広尾、白金)など近隣にお住まい・お勤めの方々にも多くご利用いただいております。
当院では、患者様の不安に寄り添い、迅速で正確な検査を提供しています。
- 不安な日の当日検査OK:思い立ったその日にご予約・ご来院いただけます。感染機会の当日でも、まずはご相談ください。必要に応じて、2週間後の再検査までしっかりフォローアップします。
- 高感度なNAAT(PCR法)を導入:尿、ご自身で採取する膣スワブ、のど、直腸など、接触のあった部位に応じた精度の高い検査が可能です。
- パートナーへの配慮と再検査リマインド:パートナーの方と同時にケアを進めることの重要性をお伝えし、約3か月後の再検査時期にはリマインドも行っています。
- プライバシーを徹底:Webで24時間予約が完結し、院内では他の患者様と顔を合わせにくい動線を確保。安心してご相談いただける環境を整えています。
モイストクリニック(恵比寿)のご案内
モイストクリニックは、東京都渋谷区恵比寿にある【性感染症・男性科・婦人科】の専門クリニックです。
プライバシーに配慮した診療体制で、初めての方でも安心してご相談いただけます。
当院では、対面・オンラインのどちらでも診療が可能。お仕事やご予定の合間でも受診しやすいよう、平日夜間(22時まで)や土日祝日も診療しています。
LINE公式アカウントでは、
🟢 ちょっとしたご相談も気軽にメッセージで受付中
🟢 検査・診療のご予約もLINEから24時間OK
🟢 受診に関するご質問も匿名でOK
と、身近なパートナーとしていつでもご利用いただけます。
まずはお気軽にLINEで友だち追加してみてください👇
▶ LINEで友だち登録する
【アクセス】
〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-2-1 エビスマンション610
(JR「恵比寿駅」西口より徒歩3分)
➡️ クリニックへの詳しい道順はこちら
【ご予約・お問い合わせ】
📱 LINE: @696ufkcc(友だち追加で予約・相談OK)
📞 電話:050-8885-0783(「ホームページを見た」とお伝えいただけるとスムーズです)
💻 Web予約:LINEから24時間受付中!
症状に心当たりのある方や不安がある方も、ぜひ一度ご相談ください。
モイストクリニックは、あなたの健康と安心のために、丁寧にサポートいたします。
🔖 監修者情報

監修:泌尿器科医 王野(モイストクリニック)
国立信州大学医学部医学科を卒業後、川崎市立井田病院にて初期研修を修了。都内大学病院の泌尿器科に入局し、性感染症分野で専門性を深める。
日本性感染症学会、日本感染症学会、日本性機能学会などに所属し、現在は薬剤耐性淋菌に対する新規抗生剤の研究に携わりながら、性感染症および泌尿器科疾患の診療にあたっている。
🖊️ この記事の執筆者

執筆:泌尿器科医 宮田(モイストクリニック)
国立信州大学医学部医学科を卒業後、川崎市立井田病院にて初期研修を修了。都内大学病院の泌尿器科に入局し、性感染症分野で専門性を深める。
日本性感染症学会、日本感染症学会、日本性機能学会などに所属し、現在は薬剤耐性淋菌に対する新規抗生剤の研究に携わりながら、性感染症および泌尿器科疾患の診療にあたっている。