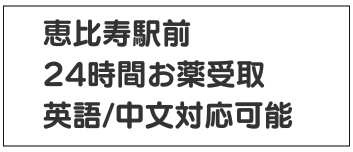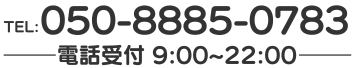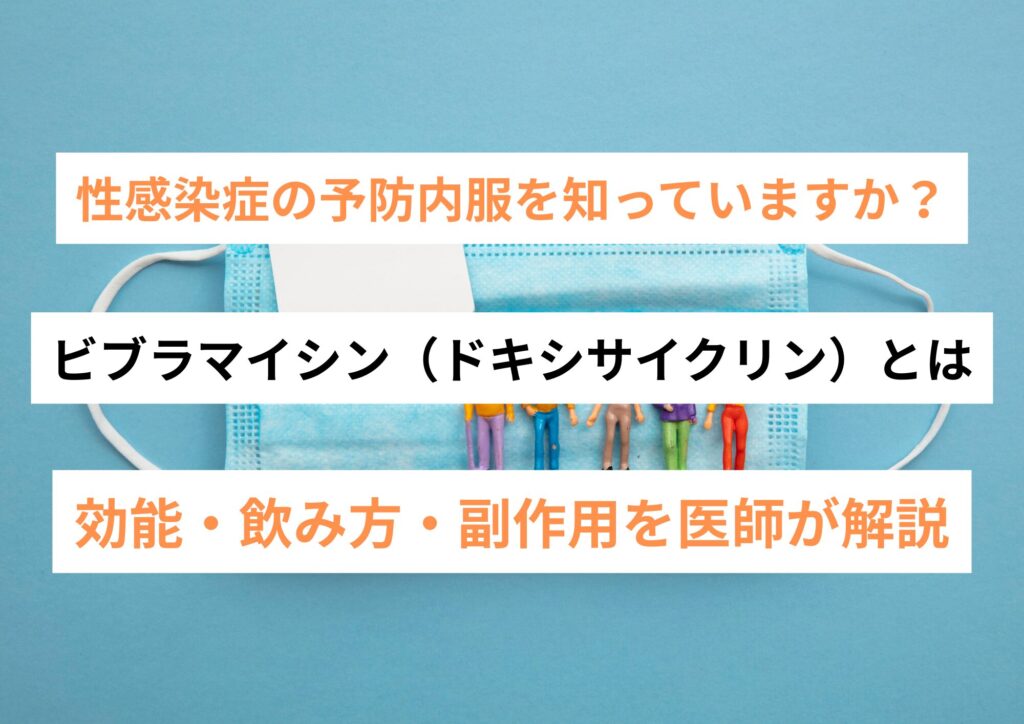
「ドキシペップ(Doxy-PEP)」という言葉を耳にして、そのお薬について詳しく知りたいと思っていませんか?
ドキシペップに使われるビブラマイシン(一般名:ドキシサイクリン)は、性感染症(STD)をはじめ、皮膚科や呼吸器内科など幅広い領域で長年使われてきた信頼性の高い抗菌薬です。
この記事では、
- ビブラマイシンって、そもそもどんな薬?
- 正しい飲み方と、注意すべき副作用は?
- 他の薬やサプリとの飲み合わせは大丈夫?
- 話題の「ドキシペップ」って何?
といった疑問について、性感染症専門クリニックの医師が分かりやすく解説します。
お薬を処方されて不安な方も、予防内服に関心がある方も、ぜひご一読ください。
ビブラマイシン(ドキシサイクリン)ってどんな薬?
ビブラマイシン(一般名:ドキシサイクリン)は、テトラサイクリン系に分類される抗菌薬です。細菌が増殖するために必要なたんぱく質を作れないようにすることで、その働きを抑えます。
ウイルスには効果がなく、あくまで細菌による感染症の治療に使われるお薬です。
作用の仕組み(作用機序)
細菌の細胞内にある「30Sリボソーム」という部分に結合し、たんぱく質の合成をブロックします。これにより細菌の増殖を止める、「静菌的」な作用を示します。
(※菌を直接殺す「殺菌的」作用とは区別されます)
どんな感染症に使うの?
非常に幅広い細菌に効果があるため、様々な感染症治療で利用されます。
- 性感染症(STD):クラミジア感染症、淋菌感染症(他の薬剤と併用)など
- 皮膚感染症:ニキビ(尋常性ざ瘡)など
- 呼吸器感染症:マイコプラズマ肺炎、百日咳など
- その他:尿路感染症、眼科感染症、耳鼻科領域の感染症、炭疽、つつが虫病、ペストなど
特に当院のような性感染症専門クリニックでは、クラミジア治療の第一選択薬として、また淋病治療の補助として処方する機会が多い薬剤です。
飲み方(用法・用量の基本)
お薬の効果を最大限に引き出し、副作用を最小限にするために、正しい飲み方を守ることが大切です。
成人の基本用量(性感染症治療の場合)
性感染症、特にクラミジア感染症の治療では、以下が基本的な飲み方となります。
- 1回100mg錠を1日2回(例:朝・夕食後)、7日間服用します。
症状が改善しても、処方された分は必ず最後まで飲み切ることが重要です。途中でやめてしまうと、菌が生き残り再発や耐性菌の原因となる可能性があります。
※他の疾患や患者様の状態によっては用法・用量が異なります。必ず医師の指示に従ってください。
※ジェネリック医薬品である「ドキシサイクリン塩酸塩錠」も、成分は同じです。
服用の3つのコツ
- 多めの水(コップ1杯以上)で飲む
- 服用後すぐには横にならない(できれば30分程度)
→ 食道に錠剤が留まると、そこで溶けて潰瘍(かいよう)を作ることがあるためです。 - 特定のサプリや薬とは時間をあける
→ 下記「飲み合わせ」で詳しく解説します。
よくある副作用と対処法
主な副作用と、医療機関を受診すべき症状の目安を知っておきましょう。
注意したい主な副作用
- 消化器症状:吐き気、食欲不振、腹痛、下痢など。
- 食道炎・食道潰瘍:お薬が食道に留まることで起こります。上記の「服用のコツ」を守ることで予防できます。
- 光線過敏症:日光(紫外線)に当たった皮膚が、赤くなったり、ヒリヒリしたり、発疹が出たりします。
すぐに受診が必要な症状
以下のような症状が現れた場合は、服用を中止して速やかに医師・薬剤師に相談してください。
- 強いアレルギー症状:発疹、じんましん、息苦しさ、顔や唇の腫れ
- 激しい腹痛や、水のような下痢が続く場合(偽膜性大腸炎の可能性)
- 皮膚や白目が黄色くなる、尿が濃くなる(肝機能障害の可能性)
飲み合わせ(相互作用)に注意が必要な薬
ビブラマイシンは、一部の薬やサプリメントと一緒に飲むと効果が弱まったり、逆に相手の薬の作用を強めてしまったりすることがあります。
| 相互作用の種類 | 対象となる薬・サプリの例 | 対処法 |
|---|---|---|
| 効果が弱まる | カルシウム、マグネシウム、アルミニウム、鉄、ビスマスなどを含む胃薬(制酸剤)やサプリメント | 服用時間を2〜4時間あける |
| カルバマゼピン、フェニトイン、リファンピシン、バルビツール酸系薬剤(てんかんや結核の薬) | 医師に服薬中の薬を必ず伝える | |
| 相手の薬が強く効きすぎる | ワルファリン(血液をサラサラにする薬) | 医師による慎重な管理が必要 |
| SU剤(一部の血糖降下薬) | 低血糖のリスクが報告されている | |
| 効果が弱まる可能性 | 経口避妊薬(低用量ピル) | 念のため、他の避妊法も併用する |
自己判断で服用を中止したりせず、必ず医師や薬剤師にご相談ください。
ビブラマイシンが使えない/特に注意が必要な方
- テトラサイクリン系薬剤でアレルギーを起こしたことがある方
- 妊娠中の方(特に妊娠後期)
- 授乳中の方
- 8歳未満の小児
→ 歯の象牙質に色素が沈着し、歯が黄色〜灰色っぽくなる「歯牙着色」を起こす可能性があるため、原則として使用しません。 - 食道の通過に障害がある方(食道潰瘍のリスクが高まります)
腎臓・肝臓への影響
ドキシサイクリンは主に肝臓で代謝され、便や尿から排泄されます。他のテトラサイクリン系薬剤に比べ、腎臓への負担が少ないとされており、腎機能が低下している方でも比較的使いやすい特徴があります。(ただし、最終的な判断は医師が行います)
服用後、血中濃度がピークに達する時間(Tmax)は約2〜4時間、体内で薬の濃度が半分になる時間(半減期)は約18〜22時間と長く、1日1回服用でも効果が持続しやすい設計になっています。
ちょっとした歴史
ビブラマイシンは1967年に米国で承認された、歴史のある抗菌薬です。従来のテトラサイクリン系薬剤よりも「食事の影響を受けにくく、効果が長く続く」という特徴から、第二世代テトラサイクリンの代表格として世界中で広く使われ続けています。
【話題】性感染症の予防内服「ドキシペップ(Doxy-PEP)」とは
最近、海外のニュースなどで話題になっているのが「ドキシペップ(Doxy-PEP)」です。
これは、性行為の後(曝露後)にドキシサイクリンを予防的に内服することで、特定の性感染症(梅毒、クラミジア、淋病)への感染リスクを低減させるという方法です。海外の一部のガイドラインでは、リスクが高い特定の集団(MSM:男性と性行為をする男性、トランスジェンダー女性など)に対して、選択肢の一つとして推奨され始めています。
ただし、日本ではまだ性感染症の予防目的での使用は承認されておらず、保険適用外(自費診療)となります。また、耐性菌の増加や腸内細菌への影響といった懸念点も議論されています。
当院では、最新の知見に基づき、そのメリット・デメリットを丁寧にご説明した上で、希望される方には医師との相談の上で処方を検討しています。
モイストクリニック(恵比寿)のご案内
モイストクリニックは、東京都渋谷区恵比寿にある【性感染症・男性科・婦人科】の専門クリニックです。
プライバシーに配慮した診療体制で、初めての方でも安心してご相談いただけます。
当院では、対面・オンラインのどちらでも診療が可能。お仕事やご予定の合間でも受診しやすいよう、平日夜間(22時まで)や土日祝日も診療しています。
LINE公式アカウントでは、
🟢 ちょっとしたご相談も気軽にメッセージで受付中
🟢 検査・診療のご予約もLINEから24時間OK
🟢 受診に関するご質問も匿名でOK
と、身近なパートナーとしていつでもご利用いただけます。
まずはお気軽にLINEで友だち追加してみてください👇
▶ LINEで友だち登録する
【アクセス】
〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-2-1 エビスマンション610
(JR「恵比寿駅」西口より徒歩3分)
➡️ クリニックへの詳しい道順はこちら
【ご予約・お問い合わせ】
📱 LINE: @696ufkcc(友だち追加で予約・相談OK)
📞 電話:050-8885-0783(「ホームページを見た」とお伝えいただけるとスムーズです)
💻 Web予約:LINEから24時間受付中!
症状に心当たりのある方や不安がある方も、ぜひ一度ご相談ください。
モイストクリニックは、あなたの健康と安心のために、丁寧にサポートいたします。
🔖 監修者情報

監修:泌尿器科医 王野(モイストクリニック)
国立信州大学医学部医学科を卒業後、川崎市立井田病院にて初期研修を修了。都内大学病院の泌尿器科に入局し、性感染症分野で専門性を深める。
日本性感染症学会、日本感染症学会、日本性機能学会などに所属し、現在は薬剤耐性淋菌に対する新規抗生剤の研究に携わりながら、性感染症および泌尿器科疾患の診療にあたっている。
🖊️ この記事の執筆者

執筆:泌尿器科医 宮田(モイストクリニック)
国立信州大学医学部医学科を卒業後、川崎市立井田病院にて初期研修を修了。都内大学病院の泌尿器科に入局し、性感染症分野で専門性を深める。
日本性感染症学会、日本感染症学会、日本性機能学会などに所属し、現在は薬剤耐性淋菌に対する新規抗生剤の研究に携わりながら、性感染症および泌尿器科疾患の診療にあたっている。
【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の診断・治療に代わるものではありません。実際のお薬の服用にあたっては、必ず医師の診察と指示に従ってください。